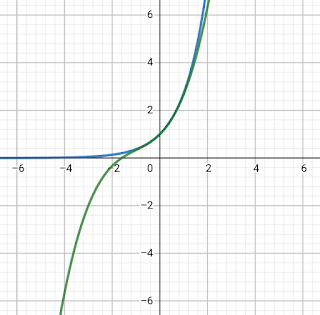微分積分⑭ ラグランジュの未定乗数法
ラグランジュの未定乗数法の計算 ラグランジュの未定乗数法って極値を求めるのに便利で、たとえば、物理では統計力学で頻繁に使います。ただ、この方法はあくまで極値の候補を求めるだけで、それが実際に極値かどうかは各点で判定する必要があります。 ラグランジュの未定乗数法の内容 ラグランジュの未定乗数法 条件$g(x,y)=0$の下で、関数$f(x,y)$の極値の候補は新たな関数 \begin{align*} L(x,y,\lambda)=f(x,y)-\lambda g(x,y) \end{align*} を設定し、 \begin{align*} \dfrac{\partial L}{\partial x}=\dfrac{\partial L}{\partial y}=\dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=0 \end{align*} を満たす点となります。 これを厳密に証明するのは難しいので、具体的な計算例を紹介します。 ラグランジュの未定乗数法の計算例題 未定乗数法を用いて極値候補を出す 以下の関数 \begin{align*} g(x,y)=2x+y-5 \end{align*} に対しての$g(x,y)$$=0$の束縛条件のもとで \begin{align*} f(x,y)=x^2+y^2 \end{align*} の極小極大を求めましょう。新しく以下の関数を設定します。 \begin{align*} L(x,y,\lambda) &=f(x,y)-\lambda g(x,y) \\ &=x^2+y^2+\lambda(2x+y-5) \end{align*} \begin{align*} \dfrac{\partial L}{\partial x}&=2x+2\lambda=2(x+\lambda)=0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial y}&=2y+\lambda =0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}&=2x+y-5=0 \end{align*} これは3元の連立方程式となります。解いてみる