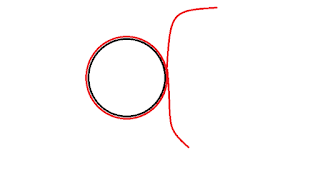偏微分方程式③ 1階特性曲線法
特性曲線法とは?その考え方 特性曲線法という考え方を紹介します。以下のような方程式の解法です。 \begin{align} a(x,y,z)\dfrac{\partial z(x,y)}{\partial x}+b(x,y,z)\dfrac{\partial z(x,y)}{\partial y}=c(x,y,z) \label{pdeeq:1} \end{align} この式だけでは全く想像ができないと思うので以下の 連鎖律 を考えましょう。 \begin{align} \dfrac{dz(x,y)}{dt}=\dfrac{\partial z(x,y)}{\partial x}\dfrac{dx}{dt}+\dfrac{\partial z(x,y)}{\partial y}\dfrac{dy}{dt} \label{pdeeq:2} \end{align} \eqref{pdeeq:1},\eqref{pdeeq:2}式を比較すれば、 \begin{align} \dfrac{dx}{dt}&=a(x,y,z)\label{pdeeq:3}\\ \dfrac{dy}{dt}&=b(x,y,z)\label{pdeeq:4}\\ \dfrac{dz}{dt}&=c(x,y,z)\label{pdeeq:5} \end{align} というような形に書くことができます。($z$について直接$t$の関数ではないので書かないでおきます.)ここで新しく表れたパラメータ$t$が重要で、この新しいパラメータにそった曲線を考えるので 特性曲線 といいます。 ラグランジュ・シャルピ方程式を用いた簡単な計算方法 新しくパラメータを設定するというのが少しハードルが高いので別の考え方があります。 \begin{align} \dfrac{dx}{a(x,y,z)}=\dfrac{dy}{b(x,y,z)}=\dfrac{dz}{c(x,y,z)} \end{align} という式から解を導くこともできます。これは変数分離形のようになっているので少しは計算しやすいかもしれませんが、計算の意味が抽象的になっています。 特性曲線法の例題を解いてみる たとえば以下のような偏微分方程式を解いてみしょう.